書籍紹介
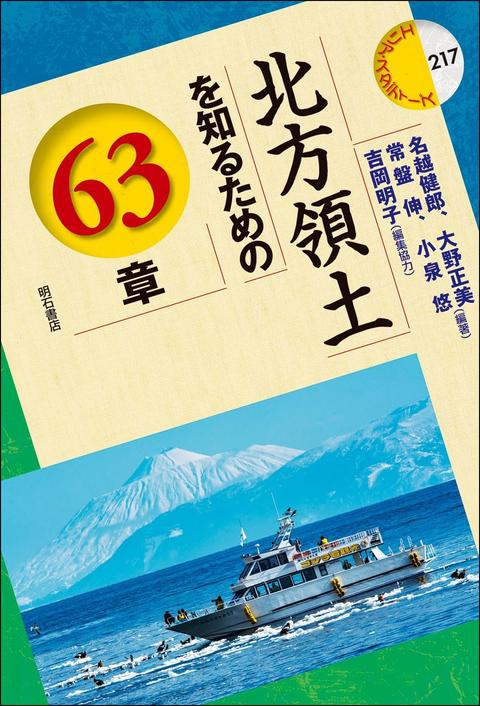
北方領土を知るための63章
名越 健郎、大野 正美、常盤 伸、小泉 悠(編著)
吉岡 明子(編集協力、24.25.26.27.28.48章執筆)
出版社 明石書店
ISBN 9784750359946
価格 本体2,400円+税
発行 2025年09月30日初版
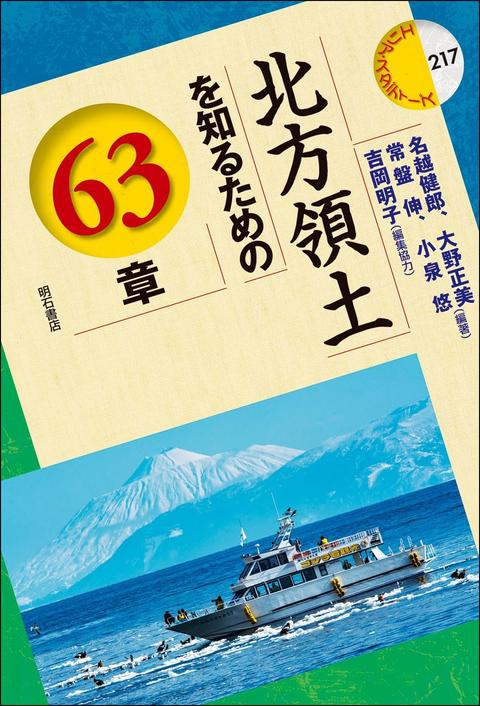
名越 健郎、大野 正美、常盤 伸、小泉 悠(編著)
吉岡 明子(編集協力、24.25.26.27.28.48章執筆)
出版社 明石書店
ISBN 9784750359946
価格 本体2,400円+税
発行 2025年09月30日初版

吉岡 明子
Akiko Yoshioka
主任研究員
旧ソ連の占領から80年を経て、日本の主権や領土保全など、北方領土の現状や歴史と未来を改めて注視すべきであろう。
本書では、返還交渉、軍事配備、ソ連占領後の統治、島の現状、島民の対日観、四島の自然や地勢・生態系、日本統治時代の生活や開発、歴史などを取り上げた。
戦後長らく四島の内情はベールに閉ざされていたが、ビザなし交流や国後、択捉で発行される地元紙の閲覧、ロシア側ネット情報の調査で島の実態を探ることが可能になった。
日露交渉が凍結された機会に、北方領土問題を洗い直し、次の機会に向けて戦略を再構築すべきだろう。本書は、そのための情報や視点を提供するのが狙いだ。(「はじめに―今なぜ北方領土なのか?」より抜粋)
はじめに――今なぜ北方領土なのか?
Ⅰ 北方領土交渉と返還運動
第1章 北方領土問題、「七つの扉」――健全な二国間関係を阻害
第2章 北方領土問題の原点――ソ連の対日参戦
【コラム1】占守島1945年8月――第二次世界大戦最後の激戦
第3章 二島返還論の起点――日ソ国交正常化交渉
第4章 凍結された北方領土問題――冷戦期の日ソ交渉
第5章 期待から失望へ――ゴルバチョフ時代
【コラム2】ゴルバチョフ政権のICJ検討文書
第6章 四島帰属交渉の基盤――エリツィンの盛衰
第7章 逆行する領土交渉――プーチンの巻き返し
第8章 崩壊した「二島幻想」――安倍・プーチン交渉
第9章 北方領土返還運動(上)――安藤陳情から冷戦期
第10章 北方領土返還運動(下)――ソ連後期からウクライナ侵攻まで
第11章 日本支持は米、EU、ウクライナ――諸外国から見た北方領土問題
Ⅱ ロシア軍配備と地政学
第12章 北方領土の戦略的価値――「軍事的に重要だから返せない」論を検証する
第13章 ソ連軍の北方領土展開――複雑に変遷した部隊配備
第14章 プーチン体制下で戦略的価値拡大――高まるオホーツク海の重要性
第15章 現在のロシア軍配備地図――択捉島と国後島における軍事力展開
第16章 北極海・オホーツク戦略との連携――連動するユーラシアの東西と結節点としての北方領土
第17章 ウクライナ戦争にも出動――テレグラム投稿と衛星画像で分析する戦争関与の実態
Ⅲ ソ連軍の占領と連邦崩壊
第18章 ソ連軍侵攻と赤いササの実の記憶――銃弾と嵐の中の脱出行、船の遭難で6人死亡
第19章 日ソ混住時代の思い出と引揚の惨状――「ソ連」への憎悪と「ソ連人」への親愛
第20章 ソ連時代の北方四島――ソ連が統治する「南クリル」の誕生
第21章 歯舞、色丹のソ連人住民退去――待たれる研究の進展
第22章 ソ連期の漁業――密漁とレポ船、貝殻島コンブ漁
【コラム3】北方領土の残置漁業権
第23章 1990年代の北方四島――ソ連邦解体で困窮する南クリル
Ⅳ ロシア支配の実相
第24章 経済と産業――漁業と水産加工業が基幹産業
第25章 クリル発展計画の虚実――実効支配強化の試みの陰で財政難
第26章 メドベージェフ大統領の国後訪問――要人の「北方領土詣で」と進む開発
第27章 経済特区の導入――「TОRクリル」「クリル経済特区」「極東の1ヘクタール」
第28章 増加する観光客――オーバーツーリズムで課題山積
第29章 ロシア人住民の四季――モミの木で始まり、モミの木で終わる
第30章 メディア――個性放つ2つの新聞
第31章 地名変更と地理学協会――正教会とも密接な関係
第32章 軍事色強まる社会――訓練、戦意高揚行事ひっきりなし
第33章 行政の混乱・腐敗――地区長の疑惑、醜聞も次々
第34章 北方領土犯罪白書――地元紙が伝える殺人・麻薬・猟奇事件
Ⅴ 北方領土の基礎知識
第35章 自然、火山、資源――洋上に浮かぶ火山の島々
第36章 地震、津波、千島海溝の巨大地震――日ロ隣接地域の防火協力に向けて
第37章 北方四島の動物――特に国後島・択捉島のヒグマについて
第38章 北方領土とラッコ――モノから生きものへ
【コラム4】タンチョウの共同追跡調査
第39章 北方領土・千島列島・クリル諸島――複雑に変遷を重ねた呼称
第40章 行政と人口(1)――日本編
第41章 行政と人口(2)――ロシア実効支配下
第42章 「歴史の呪い」残す択捉島――今はギドロストロイの「城下町」
第43章 「世界最高の温泉」国後島――同サイズ、ハワイ・オアフ島との格差
第44章 「東洋の真珠」色丹島――目立つ生活苦と開発の遅れ
第45章 「水産日本」誇示した歯舞諸島――ジェームズ・ボンドの死に場所
Ⅵ 四島交流と島民の視線
第46章 ロシアとの漁業協力――ギドロストロイ、安全操業、ウクライナ侵攻の暗雲
第47章 共同経済活動――定期的に浮上、法的枠組みで難航
第48章 ビザなし交流の明暗――日ロの領土問題のなかで果たした役割
【コラム5】ビザなし交流、15年後の大逆転
第49章 日本人墓地の現状――求められる早急な調査と修復
第50章 日本への視線――強硬論の一方、多様さも
【コラム6】ロシア人の小説、ベラルーシ人の映画
第51章 消える「日本の証」――現存する建造物は6棟
第52章 周辺地域からの視線――安全操業に揺れた歴史
第53章 北方領土対岸の歴史・文化遺産――海底ケーブルからキリスト像まで
第54章 北方領土と文芸作品――大家の歴史小説が目白押し
【コラム7】国後島でロケ「生命の冠」と原節子の替玉
【コラム8】北方領土と歌謡曲
Ⅶ 北方四島の歴史
第55章 北方四島の歴史はいつから始まるか――望まれる広い視野からの研究
第56章 クナシリ・メナシの戦いと『夷酋列像』――北方四島周辺で起きた18世紀末の大事件
【コラム9】松浦武四郎の北方四島探検と松前藩士墓
第57章 ロシア帝国の南下――幻の日本を探して
第58章 大黒屋光太夫、高田屋嘉兵衛――江戸期の国際交流
第59章 幕末の日露交渉――日本国とロシア国との境を決める
第60章 明治・大正期の千島列島――国境線の移動、先住民の衰退、行政機構の拡充
【コラム10】故郷を失った色丹島アイヌと北千島開発の先駆者、郡司成忠
第61章 明治時代の漁場開発と北方四島への移住――水産業先駆地域の形成
第62章 北方防衛と千島――対露から対米、対ソへ
第63章 戦前の北方四島――豊穣の海、のどかな桃源郷
北方領土をもっと知るための参考文献
北方領土に関係する主な条約、文書、宣言など
年表 北方領土をめぐる主なできごと