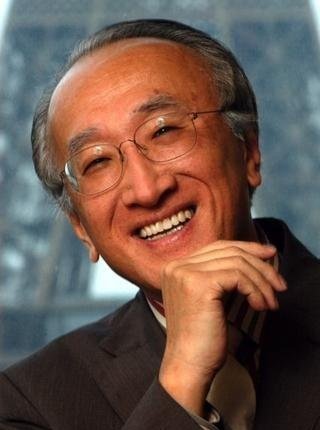要旨
日本の現実をみると、原子力利用に関して、困難な課題が山積し原子力人材も先細りの状況にある。将来の持続的成長に資する日本の原子力産業を再構築し、原子力利用を活性化するためには、今長期的な戦略の下しっかりした意思もって具体的な取組みを開始しなければならない。
2022年の中間提言では、高レベル放射性廃棄物処理、核不拡散への貢献及びリスクミニマムをポスト大型軽水炉時代の持続可能なものとするための3条件として提案したが、その後の世界と日本の環境の変化等を踏まえ、この3条件に加えて新しい状況の下で必要な課題と対応の方向性を提言する。
(1) 「原子力ビジョン」
今後原子力のライフサイクル全体を見据え、原子力を中心に据えた国家としての「原子力ビジョン」が今こそ必要である。原子力政策に関する情報を十分に開示し、透明性を確保したうえで、発電から核燃料サイクル、特にバックエンドといった原子力の専門家の意見を基礎に、社会における多くの関係者の意見を踏まえて、開かれたプロセスで議論し意見集約しなければならない。
(2) 放射性廃棄物・廃炉と高速炉
英国、フランス、米国、韓国等との国際協力体制を築き、開発や実用化に伴う時間・コスト・人材の重複を避けつつ、次世代高速炉の実用化に向けた国際協力の体制を早急に構築していくべきである。乾式再処理・高速炉サイクルに関する具体的な取り組みとして、米国アイダホ国立研究所(INL)と協力しつつ、日米韓3カ国協力で実施することが有効と考える。
(3) 国際協力
原子力利用分野で国際協力を行うのは緊急の課題である。特に同様の課題に直面し、同時に基本的な価値を共有する主要国間で国との間でサプライチェーンを共同して構築し維持していくことも今後ますます必要性が高まっていく。
(4) 円滑な金融
原子力利用に関する規制の強化や建設期間の延長等といった事業者には予見が困難なリスクへの対応として、資金調達の多様化や国が一定のリスクを負うことも検討の余地がある。
ただし、時間の制約を勘案すれば、多くを同時に追求すること自体が大きなリスクとなりうるため「次善の策」の選択も考えなければならない。具体的には、従来の政策を大転換して、原子力人材が国内にあるうちに既存原子力発電の活用と後始末、すなわち廃炉、福島デブリ処理や使用済み核燃料の管理・処理処分の課題、特に高レベル放射性廃棄物の処分に集中すべきである。
(以上)