コラム 外交・安全保障 2020.02.18
ジブチ拠点から考える情報収集目的の中東派遣
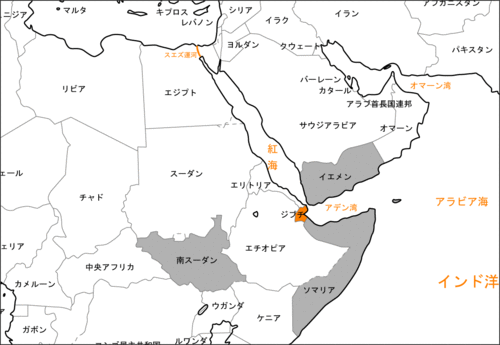
令和最初の部隊派遣の拠点
令和の時代の自衛隊部隊派遣が、防衛省設置法「調査・研究」を根拠にした情報収集活動として始まった。海上自衛隊の護衛艦たかなみと、哨戒機P3Cの中東派遣だ。
活動拠点となるのは紅海の入り口に位置し、インド洋とヨーロッパをスエズ運河経由でつなぐ要衝、ジブチ共和国に置かれた拠点だ。毎年200件近い海賊行為が行われる中で、2009年からその対処にあたる部隊の拠点として2011年に開設された。南スーダンで発生した争乱時に現地の邦人が退避する際の経由地となるなど、現在では実質的に自衛隊唯一の海外拠点として機能している。小規模ながら自衛隊ジブチ駐屯地と表現してもよいものだ。
当初の目的だった海賊対処は、警戒や取り締まりの効果が上がり、年々発生件数が低下してきた。2019年度の海賊事案の発生件数は、2015年以来、4年ぶりに0となった。
ジブチには自前の基地を置いている仏・米・中に加えて、独・伊などNATO諸国の軍隊も駐留している。海賊対処そのものを目的にした多国籍部隊としては、第151合同任務部隊(CTF151)が編成されている。派遣された海上自衛官はCTF151の指揮官を数次に渡って務めており、2月後半からも同指揮官に海上自衛官が着任する予定となっている。
およそ10年に渡る海賊対処とジブチ拠点の活動経験から考えることで、日本がこの地域で開始した新たな情報収集活動の意味について、その現実がみえてくる。
海賊対処活動の経験と部隊派遣の意味
第一に、各国の行動や情勢についての情報収集の窓口としての意味だ。
派遣にあたって様々な場で強調されてきたように、活動場所となるオマーン湾は、日本にとって海上輸送の最重要ポイントの一つだ。この地域で各国・各国軍が何を行っており、またこれからどのような活動を展開するつもりなのか、とりわけ情勢が激しく動く状況下では日常的な情報収集が非常に重要なことは理解されよう。それは日本に限らず各国にとっても同様である。
そのことは、日本が部隊を派遣していることの意味を明確にするだろう。つまり、日本が護衛艦などを派遣して活動していることは、他国にとっては日本が何をしようとしているのか否応なく気になるものだ。したがって関心をもって情報収集や意見交換に来ることになる。それは、海賊対処部隊が展開する中で、日常的に行われていた様相そのものだ。
海賊対処にあたっている自衛隊部隊は「海賊対処」専従部隊だが、各国はそうではない。海賊が減れば別の任務に戦力を振りわける。その際には自衛隊を含めた協力している各国部隊と、活動を調整することになる。こうした海賊対処を越える各国の情報が、自衛隊部隊に直接もたらされる。
今回の中東派遣も同様のものだ。仮に日本のプレゼンスがなければ、日本は常に情報を外部からもらいに行く立場となる。やや極論すれば、部隊が展開していることによって日本は、欲しい情報を持つ各国が、自ら情報交換に来てくれるチャネルを持つことができるのである。派遣部隊自らが情報を収集するのみならず、情報収集に来てもらう窓口となる、これが第一の意味だ。
第二に、有事の際の即応準備がある。この点については、とくに批判的な声が聞かれる。不安定な地域に派遣することで、護衛艦等が攻撃されるリスクがあるというものだ。 2020年年初に起きたイランと米国との緊張の高まりは一旦回避された。しかし今後の展開は読み通せない。もとより偶発的な衝突の危険性は依然として存在する。大きな軍事的衝突などが発生した場合には、平和安全法制の審議過程で検討されたように、存立危機事態や重要影響事態の認定が検討されることになる。
しかし平和安全法制は施行されたとは言っても、実際には極めて使いづらい法律だ。何か事が起こった際には情報収集を行ない、原則として国会審議を経て、重要影響事態や存立危機事態の認定が行われる形となっている。
また、実際の部隊展開にはさらに時間を要する。たとえば9・11後のイラク戦争の際には、派遣の根拠法成立から部隊派遣までに実に5ヵ月近くを要した。平和安全法制を適用するにしても、仮に何かが発生して事態認定が為された場合、近隣に所在する護衛艦や部隊を派遣できるようにしておくことで初めて機能するものなのだ。
キヤノングローバル戦略研究所(CIGS)ではこれまで様々な危機を想定したシミュレーションを実施してきたが、度々露わになるのは情報収集目的等での予備的な部隊展開や、他の活動に従事している部隊の転用が、速やかな派遣実施の前提となる様相だ。つまり、そのこと自体の賛否はあろうが、危機が発生した際に迅速な対応を可能とする準備としての部隊展開が、第二の意味としてある。
第三は、アデン湾からアラビア海の南シナ海化の防止だ。周知のように日本はインド太平洋戦略(構想)を掲げてきた。この構想の焦点に中国があることは指摘するまでもない。
その中国は2017年からジブチに数千人規模の人民解放軍の部隊を展開し、同軍初の海外基地の整備・拡大を続けている。当然ながらジブチの旧宗主国フランスを初め、ジブチに展開している各国は、中国が何をしようとしているのか気にしてきた。実際に中国軍の展開とあわせて中国は莫大な投資や援助をジブチに展開している。欧州諸国からすれば、自らの勢力エリアに初めて中国軍が進出してきた事態でもある。
南シナ海では、中国が進めた強引な現状変更が地域の緊張を高めてきた。九段線の主張や、2013年に一方的に中国が行った防空識別圏の設定などは記憶に新しい。これらの事態が、ジブチやソマリア沖で発生することは何を意味するか。ジブチの位置は、欧州からみれば、スエズ運河、紅海を抜けて、インド洋、その先のアジアと結ぶ大動脈だ。ここを一方的なルール等によって通行に支障を来したりされることは許容できるものではない。
ジブチにおける中国軍の存在は、中国がアジアで進めてきた軍事力を背景にした一方的な現状変更が、初めてリアリティーをもってアジア域外に展開しているものといえる。
こうした視点を共有し、各国と協調してそれを防止していく。それは、欧州・中東の事象にアジアの文脈を載せて共有するものでもある。実際に海賊対処部隊は、各国との情報交換等をつうじて、間接的にその役割を果たしてきた。アデン湾からアラビア海にかけての南シナ海化の防止と、そのストーリーの共有、それが第三の意義だろう。
第四に、これらを包含することによって情報収集の場としてのジブチ拠点を維持することがある。前述のとおり、ジブチ拠点は海賊対処にあたる海上自衛隊部隊の活動拠点として整備されている。しかし海賊の発生件数は相当程度少なくっている中で、拠点をどうするのかが近年、課題となってきた。
当初の目的を達成したのであれば撤退すればよい。しかし海賊は根絶されたわけでもなく、隣国ソマリアやイエメンが安定する見込みもない。もし撤退後に再び海賊対処が必要になったとき、再派遣のコストは高くつくものとなる。実際問題としては、ジブチで自衛隊が拠点を置く場所は、空港脇の立地のよい場所にある。したがって自衛隊が撤退した場合には、別の国が新たに租借するだろう。前述のとおり情報収集拠点としても重要な意味があることは把握されており、撤収という選択肢は日本にはほとんどない。
このために中東や北アフリカにおける邦人保護の拠点としたり、能力構築支援の拠点としたりと拠点の活用が模索されてきた。今回の情報収集目的による派遣の拠点とは、実際に担ってきた役割でもあり、拠点維持という観点からは渡りに船でもあるといってよい。
意義と根拠のギャップ
ここまで新たな派遣の意味をみてきた。日本がこの地域で正確な情報を収集し、情勢判断と対応検討の材料を増やすことの意味は強調してもしきれないほどだ。もとより派遣された護衛艦や哨戒機が自ら収集するものは限られよう。しかし護衛艦そのものが行う情報収集よりも(それ自体が無意味という意味ではない)、部隊が所在し、活動していることでもたらされるものに意味があるといってよい。
しかし、防衛省設置法「調査・研究」を根拠に実戦部隊を派遣するのは、根拠法の濫用といわざるを得ない。それは9・11後に行われた東京湾での事実上の米空母護衛時の対応を想起するものだ。強い批判が寄せられ、自衛隊海外派遣を正面から議論できなくする一つの要因となってきたものである。それを今また繰り返すことは筋悪の対応と言うほかない。他に法的根拠が見当たらないことは事実だ。しかし設置法でいわば強引に派遣したことで、議論する環境がさらに失われることとなる。
国連PKO法、国際緊急援助隊法、海賊対処を含めた様々な特措法に加えて国際平和支援法など、自衛隊海外派遣について様々な根拠法が平成の時代に作られた。所掌業務に国際協力も加えられた。それらを経て、今また「調査・研究」で海外派遣が行われる。
一体それはなぜなのか。
一つの答えは、平和安全法制にせよ、その他の法的枠組みにせよ、既に国際社会に存在する枠組みや活動に貢献するために派遣を行う枠組みだからだろう。つまり、海賊の存在(海賊対処法)、紛争とPKO等の存在(国連PKO法)、或いはイラク戦争(イラク特措法)といった形で、国際社会が対処する課題を踏まえて、日本がそれらに対して自衛隊による協力を要請される場合に備えるものとして法律は整備されてきた。言い換えれば、日本が主体的・能動的に何かを行うことはほとんど考慮されていない。
そのことは、今回の派遣が突きつけているのは自衛隊海外派遣を巡る議論というよりも、日本がどのような国際社会を望み、そのために自ら何を行うのかの議論の必要性だ。つまり平和安全法制の際に脇に追いやられた論点「日本は世界で何を目指し、そのために何をするのか」ということの不在が浮かび上がる派遣でもある。
令和の時代の自衛隊海外派遣
結果として何のための派遣か明確化されぬまま、一般論として危険な地域に自衛隊が派遣される。そのしわ寄せは現場の自衛官にのしかかってくることになるだろう。これまでの海外派遣でも派遣された自衛官は、何のための活動なのか自らを納得させて活動してきた。
今回の派遣でも自衛官は、たとえば情報収集や意見交換を行う各国軍関係者らに対して、いったい日本は何のために、どのような目的で部隊を出しているのか、また有事にはどう対応することになるのか、それを公式・非公式に説明することが求められることになる。国民的議論が不在のなか、派遣された要員が自ら考えて模索し、気づきをフィードバックするしかない現実がそこにある。
昨年、これから海上自衛官として活躍していく幹部自衛官の訓練を任務に、世界を回る練習艦隊に乗船する機会を得た。乗船時、練習艦隊は、CTF151の指揮官を務めた梶元大介海将補が司令官を務めていた。海賊対処など多国籍部隊で活動しながら、自ら活動意義を模索した経験を持つ自衛官らが、後輩たちにその経験を直接つなぐことで、日本の国際社会における取り組みはかろうじて成り立ってきた。それが健全な姿とは思わないが、令和の時代もこれまでと同じその様相が続くだろうことを、今回の派遣は示しているように思える。
