メディア掲載 国際交流 2015.02.04
中国市場の構造変化と日本企業のチャンス拡大
前回は2010年以降、中国において所得の急速な増大により巨大な国内市場が出現し、国際競争力のある日本企業は高付加価値製品の販売を伸ばして成功を収めていることを紹介した。今回はこの中国国内市場が日本企業および日本経済に及ぼす影響について述べる。
中国に精通している日本企業の間では、中国の大都市において一人あたりのGDPが1万ドルに達すると、その地域で日本企業の様々な製品・サービスに対する需要が急速に拡大することが経験的に知られている。代表的な例を挙げれば、紙おむつ、粉ミルク、哺乳瓶、エアコン、空気清浄機、テレビ、文房具、衣類、コンビニ、日本食レストランなど、広範な製品・サービス分野で見られる現象である。
日本社会の所得分布が均質であることから、大半の日本企業の製品・サービスは外国企業に比べて比較的所得レンジの狭い、日本人の平均的な所得階層の顧客をターゲットとしている。このため中国の消費者にとって、以前は品質の良さを理解できても値段が高過ぎて手が出なかった。しかし、一旦日本人並みの所得水準に到達すると、高い品質の商品に対して値頃感が感じられるようになり、日本企業が提供する製品・サービスに対する需要が急拡大する。その境目が上述の1万ドルである。
円ドル相場によって大きく変化するが、1万ドルを約100万円とすれば、両親に子供一人の3人家族で、その都市の平均年収が300万円程度に達することを意味する。中国は貧富の格差が大きいため、平均年収が300万円に達した地域では年収が500万円以上に達する世帯もかなりの割合に達する。その程度の年収であれば、日本の製品・サービスを無理なく購入できるのは十分理解できる。
しかも、中国の名目成長率は2004年から2011年までの8年間、2005年(15.7%)と2009年(8.7%)を除き、17~22%という先進国の常識では信じられないような高い伸びを維持していた。このため、沿海部の先行発展都市と内陸部の後発都市との間で大きな所得格差があっても、先行発展都市の一人当たりGDPが1万ドルに達した後、数年以内に後発都市がその水準に到達することは珍しくない。
図表1は、一人当たりGDPが1万ドルに達した都市を年ごとに整理して一覧表にしたものである。2007年に蘇州、無錫、深圳の3都市が初めて1万ドルに達した後、大都市が毎年続々と1万ドルに到達しているのは、この名目成長率の高さによるものである。つまり、日本企業の潜在的な顧客層は、地域的にも日本の常識では想像もつかない速さで、急速に広がり続けている。
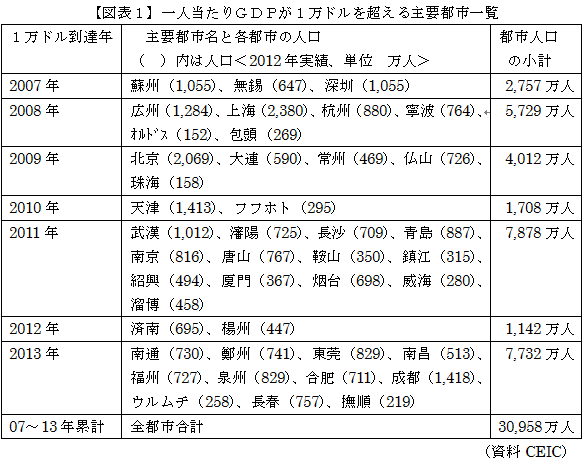
これほど大きな変化が生じていたにもかかわらず、2007年から2009年までの3年間は、中国経済自身が景気過熱によるインフレ、厳しい引き締め政策による急減速、リーマンショックによる景気失速、そして強力な景気刺激策による急回復と激変が続いたため、日本企業も中国市場で進行していた上記の構造変化に気が付かなかった。
2010年になって中国経済が落ち着きを取り戻すと、中国の沿海部主要都市において日本製品・サービスに対する需要が急拡大していることに多くの日本企業が気付いた。当時、欧米企業はリーマンショック後のバブル経済崩壊の泥沼から十分回復できていなかったのに対し、日本企業は欧米のバブル経済からある程度距離を置いていたため、バブル崩壊のダメージが軽く、回復も比較的早かった。
図表2で見ると、世界の主要国の中で日本企業だけが2011年以降、対中直接投資を急増させている。この統計には1年近いタイムラグがあることから、実際には2010年以降、日本企業の対中投資が積極化していたことを示している。
2012年9月以降、尖閣諸島の領有権問題を巡り日中関係が最悪の状況に陥り、日本企業の間でチャイナリスクに対する警戒感が急速に高まったことから、2013年の対中直接投資は激減した。
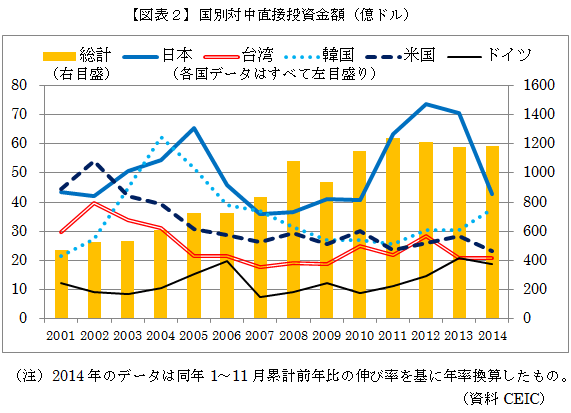
しかし、2014年初以降、中国政府は対日外交に関して政経分離の方針を明確に打ち出し、日本企業に対する誘致を積極化させたため、日本企業の間でも徐々に安心感が広がりつつある。加えて、今後の中国市場における1万ドルクラブの都市人口、すなわち日本企業にとっての潜在的顧客数が2020年には7~8億人に達すると考えられ、世界中の主要企業が市場開拓を競っている。これほど重要な市場を主要な日本企業が軽視するとは思えないことから、直接投資の回復は時間の問題であると考えられる。
大半の日本企業が中国に対する投資姿勢を慎重化させたこの2年間に内陸部の後発都市でも、高速道路や高速鉄道等のインフラ建設により投資環境が好転し、産業集積の急速な拡大が生じた。その結果、内陸部でも1万ドルクラブ入りする都市が増加している。日本企業の多くは中国からアセアン諸国に関心を移していたため、チャンスが内陸部に拡大していることに気づいていない。今後この変化に気付く日本企業が徐々に増え、それとともに内陸部での投資スタンスを積極させていくことが予想される。なお、筆者の手許の計算によれば、日本の対中直接投資金額は1~10月累計では前年を40%以上下回っていたが、11月単月で見ると前年比+31%のプラスに転じている。
今後の中国市場を展望すれば、日本企業にとって追い風となるいくつかの好材料が出てくると予想することができる。
第1に、「80後(中国語の発音はバーリンホウ)」と呼ばれる、1980年以降に生まれた新世代の影響力の増大である。彼らは生まれた時から高度成長時代だったため豊かな経済しか知らない。しかも、半数近くが都市で育ち、相対的に学歴が高く、外国との接点も多く、情報量も豊富である。このためグローバルスタンダードの考え方をほぼ共有しており、旧世代に比べて、知財保護、資金決済の期日の遵守、マナーの重視などの面において、先進国の常識が自然に身についている。
現在彼らは35歳以下であるが、今後10年の間に急速に中国経済の重要な担い手となっていく。それに伴い日本企業も安心して付き合うことができる中国人のビジネスパーソンが増えていくことになる。
第2に、アベノミクスの副産物として生じた円安である。この円安によって、すでに一部の企業は生産拠点を中国から日本に戻す、あるいは中国に移す計画を中止するといった動きを示している。日本で生産して採算が取れるようになれば、中国市場への参入のハードルが下がるのは明らかである。日本経済にとっても雇用創出、設備投資拡大のメリットが及ぶ。
それに加えて、円安は中国人の日本旅行ブームを加速させている。日本を訪問する中国人旅客数は2013年の131万人から、2014年は240万人に達する勢いで急増しており、2015年以降もその勢いは止まりそうもない。中国人が日本で消費する金額は他の外国人に比べて格段に大きい。その恩恵で、2014年の日本の旅行収支は5月、7月、および11月に黒字となった。これは大阪万博が開催された1972年4月以来の出来事である。2015年は通年でも旅行収支が黒字になる可能性がある。これが日本各地の観光地を活性化させ、地方創生を後押しするのは言うまでもない。
もしこの円安が今後数年続くと、その間に中国の賃金上昇等を背景に中国での生産コストは2013年対比2倍近くまで上昇する。そうなれば日本と中国の生産コストの格差は劇的に縮小し、多くの日本企業が中長期の生産拠点立地計画の考え方を抜本的に改め、日本で生産し中国に輸出する経営方式が構造的に定着する可能性も小さくない。
ただし、その場合でも、中国市場における販路を確保できていなければ何のメリットも生じない。中国での販路拡大の成否が決定的に重要である。
中国市場における販路拡大は日本人の力だけでは難しい。優秀な中国人リーダー、あるいは中国市場に精通した台湾人・香港人との提携が不可欠である。この提携を成功させるには内向きの傾向が強い多くの日本企業の経営戦略・組織改革が必要になる。
次回はこの点について詳しく述べることとする。
