コラム 2019.10.09
価値観の変遷と川端康成
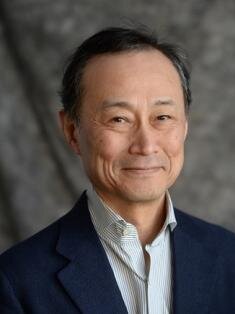
先日、アメリカの雑誌『New Yorker』をブラウズしていたら、ルノワール展の紹介記事が目にとまった("Renoir's Problem
Nudes", 8 月26 日号)。その記事で引用されている女性の美術史家によると、現代ではルノワールという名はsexist male artist の代名詞で、特に後期の裸婦画は、直視に耐えないそうだ。
法令不遡及の原則というものがある。過去の行為に現在の法律が適用されないのには合理的理由がある。しかし法律と違い、現在の価値観は、否応なく過去を裁く。
#Me Too 運動の盛り上がりとともに、業界の頂点に君臨し権力を振るってきた男性が、セクハラで訴えられ失脚する例が後を絶たない。常習犯の噂が絶えなかったハリウッドの超大物プロデューサーが去年捕まった。これは一見法令不遡及と矛盾するようだが、彼が過去に重ねてきた不法行為の被害者が声を上げ始め、それに押されて司法当局が動いたようだ。現在の価値観が過去を裁いた例と言える。
川端康成がノーベル賞を受賞して間もない頃、高校の現国(今では「現代文」と呼ぶらしい)の先生に『雪国』を勧められた。どの程度読んだのか怪しいが、叙情的な文章とはこういうものか、という程度の感想しかなかった。ところが近年再読する機会があり、全く違う視点からの感想を持った。
再読のきっかけは、往年の映画版(1957 年、岸恵子・池部良主演)を何かの拍子で観て、文庫本を手に真冬の湯沢を訪れたことだ。駅前の通りはお湯が常時流され雪は積もらない。住み手にとっては進歩かもしれないが、映画に収められた白一色の雪国の情景は失われてしまった。舞台となった旅館もバブルの初期に建て替えられ昔の風情はない。ただ、その旅館に、『雪国』の執筆に使われた部屋が保存されており、かなり充実した関連資料が展示されている。
周知のように『雪国』は、温泉芸者である駒子の片思いの物語である。高等遊民の島村は、ふらりと一人で湯沢に現れ、駒子と出会う。しばらく逗留の後、妻のいる東京に帰る。また戻ってくると約束した日には現れない。音信はない。季節が変わった頃突然戻ってきて駒子をお座敷に呼ぶ。花代は払うが彼女の困窮を目の当たりにしても援助はしない。
旅館の展示資料にあった新聞記事によると、駒子は実在の人物(実名は異なる)で、発表された小説が実体験にあまりにも似ているので困惑した。これを知った川端は、駒子に詫び状を自筆原稿と共に送った。残念ながらその詫び状と原稿は駒子が焼き捨てたので残っていない。(駒子のモデルの女性については、村松友視の『「雪国」あそび』に詳しい。)
実話なのであれば、島村のやったことは、すなわち川端康成のやったことだ。当時は社会的に許される行為だったのかもしれないが、女性をリスペクトする現在の価値観ではどう裁かれるのだろうか。